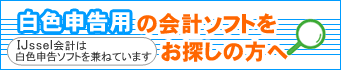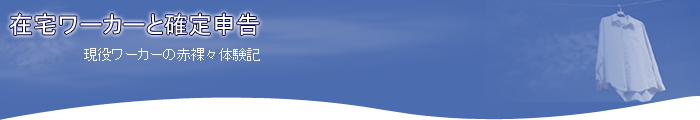第1回 専業主婦から在宅ワーカーへ
税金に無頓着でいられた頃
結婚して出産するまではずっと会社員をしていました。年末調整の時だけ還付金という名目であらわれる税金に「得した♪」と、ただ単純に喜んでいました。実際は得なんてしていなかったのにね。
専業主婦時代も所得税や住民税は、ぜ〜んぶ夫の会社が処理してくれましたから、引き続き無頓着。相変わらず、年末の還付金にニンマリしていました。
そんな私が、娘の幼稚園を機に在宅ワーカーを開始。初年度は働いた金額も少ないし、申告の必要はないだろう、と思っていたら....。
えっ!所得が38万円を超えると申告しなければならないの?
この年、仕事を請けていた会社数社のうち1社だけに源泉徴収されていました。
「申告の必要はないと思ったけど、この引かれた所得税を還付してもらうために、申告するぞ!」
あくまで、還付してもらうことだけを考えて、申告に関するサイトをいろいろ見て回っていたら、とんでもない勘違いが発覚しました。
「仕事を請け負い報酬を得ている場合、所得が38万円を超えると確定申告が必要になる」
ええーー?所得が38万円?!103万円じゃないの?
この年、収入が80万円ほどあった私は大慌て。
必要経費はざっと見積もっても20万円。
80万円(収入) − 20万円(経費) = 60万円(所得)
38万円なんてとっくに超えている!
収入は、その年に仕事をして得たお金の合計です。つまり「売上」のことです。
所得は、収入から経費を引いた金額です。
在宅ワーカーの場合、103万円の壁はまず関係ありません
私は、パートに出ている人たちでよく使われる「103万円の壁」を、自分にもあてはめ ていたのです。
パートの場合は、基本的に会社員と同じで「給与所得控除」というものがあります。 「65万円の給与所得控除」に「38万円の基礎控除」を加えた「103万円」までは所得税がかからないのです>在宅ワーカーとして確定申告をはじめてから、この65万円の給与所得控除がうらやましい限り。
私のように、自分で仕事を請けて報酬を得ている在宅ワーカーに「給与所得控除」はないのです。
ただし、例外もあります。
「家内労働者等の必要経費の特例」により、65万円の控除が受けられる場合もあるそうです。
※家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
在宅ワーカーは最後の部分にあてはまりそうですが、必ず、管轄の税務署に問合せし、判断してもらってください。
私の場合は、1個人と4社から仕事を請けていましたので、「家内労働者等の必要経費の特例」にはあてはまりません。
この年の収入は、潔く(?)、確定申告することになったのでした。
夫の扶養を外れるか否かの心配
申告が決定してからというのも、次に心配になってきたのは夫の扶養を外れるかどうかということ。
結果からお話すると、60万円の所得があった私は、所得税法上は夫の扶養に片足だけつっこんでいられました(ほとんどなしに近いといったほうが正解かな)。社会保険では、今まで通り扶養のままでいられました。
夫の会社は社会保険の扶養を外れなければ家族手当がつきましたが、家族手当がつくかどうかは会社によって違うようです。
・38万円の配偶者控除が受けられなくなりました。
・配偶者特別控除が若干受けられました。
夫の社会保険は扶養のまま
配偶者の合計所得が130万円未満の場合は、夫の社会保険の扶養のままでいられます。
夫の社会保険から外れるということは、自分で国民健康保険や国民年金などを支払わなければならなくなりますが、この支払い金額は相当大きく、支払った場合は手取りがぐっと減ってしまいます。
小さい子どもなどがいてあまり大きな仕事ができない在宅ワーカーの場合は、所得を130万円未満に抑えたほうが賢明といえるかもしれません。
読んでいただきましてありがとうございました。次回、第2回目は「はじめての白色申告」を予定しています。お楽しみに!
| 前へ | 次へ |
2001年から在宅ワークを開始。さまざまな業務を経て、2004年からはWEB制作のみで活動しています。手がけるサイトは小規模サイト。成果を出すことを常に意識しながら、制作と運営を請けています。